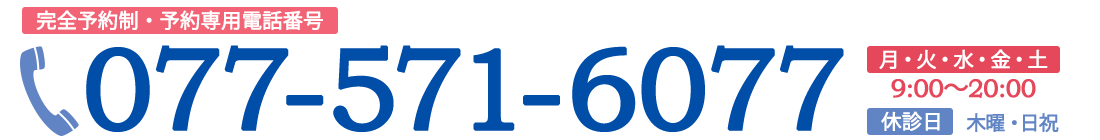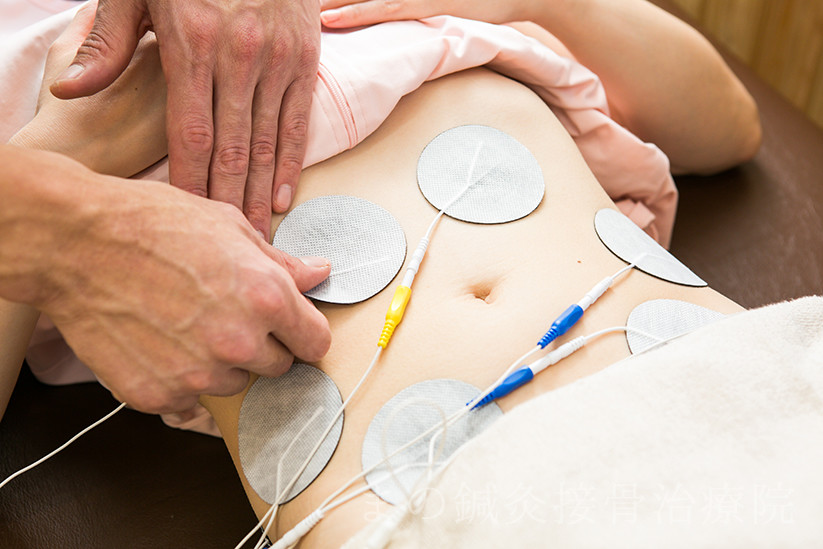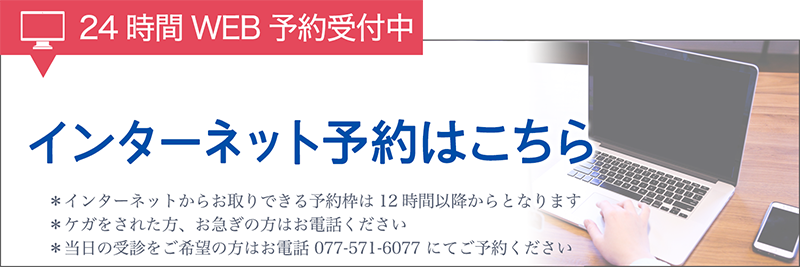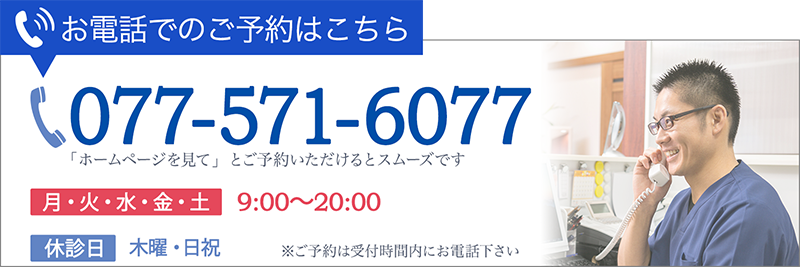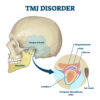目次
肩コリでお悩みのあなたへ
今このホームページをご覧になっているということは、つらい肩コリで頭痛や吐き気がひどくなり「肩が重くて仕事に集中できない・・・」とお悩みなのでしょうか。マッサージや痛み止めを飲みながら、なんとかやり過ごしているのかもしれませんね。おつらいと思います。ご安心ください。
当院では「この症状は、もう治らないかもしれない…」とお悩みの患者様が来院されます。
症状の原因を見極めて体のバランスを整えることで、つらい肩コリを根本から解消することができます。あなたが「つらい肩コリをどうにかしたい」と真剣にお悩みなら、ぜひこのページを最後までお読みください。
肩コリの症状と原因
肩コリになる原因のひとつには「姿勢」が関係していると言われています。背中が丸くなり頭が前に突き出すようになると、首のまわりにある筋肉や関節に負担がかかり「頭痛・めまい・吐き気・目の疲れ・倦怠感・集中力の低下・しびれ」などの症状が現れるのです。
近年ではスマホやパソコンの普及にともない、肩コリに悩んでいる子供たちが増加している傾向にあります。実は姿勢の悪さは外見が「老けて見える」だけでなく、集中力が低下させて「メンタルにも悪い影響」をおよぼすこともあります。
鍼灸と整体をおこない「関節のひっかかり」や「神経の圧迫」が解消すると、理想的な姿勢をキープできるため肩コリを根本から治癒させることができます。つらい肩コリで「どこへ行ってもよくならない」とお悩みの方には、効果的な治療を組み合わせた当院のトータル治療が特にオススメです。
肩コリが全身におよぼす悪影響
悪い姿勢が習慣になると首や肩まわりの筋肉が硬くなり、神経や血管を圧迫するようになります。すると感覚神経を傷つけてしまい腕に「しびれ」や「冷感」などを感じることもあります。さらに背骨のゆがみが悪化して関節が痛めつけられると、「背骨の老化」が進行してしまい全身への悪い影響がでてきます。
肩コリで長年悩んでいる方ほど、背骨のゆがみによる「関節のひっかかり」や「神経の圧迫」があるため、「脳と体の神経ネットワーク」に悪い影響がでてさまざまな体調不良でお悩みのなる方も少なくないのです。
姿勢が悪くなる5つの習慣
1.デスクワーク
背中を丸くする姿勢を長時間つづけると、肩や首まわりの筋肉は不自然にひっぱられ血の流れが悪くなるため肩コリとなります。この状態が慢性化すると、悪い姿勢のまま筋肉が固まってしまい肩コリはますます悪化していきます。
2.座る
椅子に座るときに「浅く腰掛けて背もたれに寄りかかる」と、背中が丸くなり姿勢を維持するための筋力が弱くなります。すると猫背が悪化して、首肩や腰にも悪い影響がでてきます。
重い物を背負ったりヘルメットを被りっぱなしの作業をつづけると、首や肩の関節にダメージが蓄積されていきます。バイクやバレーボールのレシーブ時にとりがちな「前傾姿勢」や、激しいトレーニングによる「過度の筋力アップ」も姿勢が悪くなる原因となります。
4.スマホ
スマホやゲーム機をのぞき込む姿勢は、背中が丸くなりやすく肩コリの原因となります。画面をなるべく顔の高さまで上げて、首の負担をやわらげてあげると安心です。
5.精神や内臓の不調
ストレスがかかり悩んでいるときは、自然と背中も丸くなり姿勢が悪くなる傾向があります。実は猫背になると呼吸が浅くなり「脳が酸欠状態」になってしまうため、うつ病などの精神疾患も慢性化しやすくなるのです。
また背中が丸くなると胃が胸郭のほうまで押し上げられて「食道裂孔ヘルニア-しょくどうれっこうへるにあ」になると、心臓や肺にまで悪影響をおよぼしてしまうことがあります。
背骨や骨盤はあなたの生活習慣にあわせて、「背骨のなかにある神経」を守るために変化していきます。鍼灸と整体をおこない姿勢がよくなると、「関節のひっかかり」や「神経の圧迫」が解消されてベストな姿勢を維持できます。すると「脳と体の神経ネットワーク」がスムーズに流れるようになるため、肩コリを根本から治癒させることができるのです。ご安心ください。
当院での肩コリ治療
1.問診
肩コリといっても人により原因や症状はさまざまです。なかなか良くならない肩コリの多くは、「関節のひっかかり」や「神経の圧迫」が解消できていない方が多くおられます。また「生活習慣の癖や環境」をしっかり見極めないと、お悩みを解消するための「正しい治療方針」をたてることができません。
したがって、まずはしっかりとお話を聞かせていただき「あなたが肩コリになってしまう背景」を見極めます。
2.検査
①複合動作
筋肉や関節の状態を見極めるために、簡単な動きをおこなっていただきます。「関節の動き」や「筋肉のバランス」を見極めることで、あなたの体がどのような状態になっているのかを見極めます。
②視診
「肩や耳の高さ」や「歩行」を観察することで、あなたの背骨や骨盤がどのようにゆがんでいるかを見極めます。また肩コリが慢性化するほど、「ほくろ・多毛・発赤・乾燥肌・毛細血管」など、さまざまな所見が皮膚にもあらわれます。
③ナーブ・スコープ(温度検査)
「背骨のゆがみ」と「神経が圧迫している部位」を特殊な検査機をつかって見極めます。
神経が圧迫されると「皮膚の温度」にも左右差がでて、「ブレイク」という反応があらわれます。ブレイクは神経が圧迫しているひとつの指標となります。
④静的触診
神経圧迫をおこしている背骨のまわりには「浮腫」みが生じて、「強い痛み」を感じる部位があります。また骨盤がゆがんで背骨が捻じれると、「筋肉の硬さにも左右差」があらわれることもあります。
⑤動的触診
原因である背骨をチェックして、「正常な可動性」があるかを確認していきます。背骨がゆがんで関節のバランスが悪くなると「背骨の動きが悪くなる」のです。背骨の動きを確かめることで「関節のひっかかり」を触知できるので、「どの方向から背骨を矯正するべきか」が明確にわかるようになります。
⑥レントゲン分析
当院では医療機関で撮影されたレントゲンを分析して、背骨や骨盤のゆがみを正しく見極めることができます。分析をおこなうことで「背骨や骨盤のゆがみ」や「背骨の老化状況」がわかるので「治療期間」や「通院頻度」などが明確になり、あなたにとってベストな治療方針をたてることができるのです。
(※過去6ヵ月以内に撮影されたレントゲン画像をお持ちの方は、初診時にお持ちください)
3.治療
1.整体
客観的なデータをもとに体の状態を正しく見極めて、背骨や骨盤のゆがみをあるべき状態へと戻します。すると「関節のひっかかり」や「神経の圧迫」が解消されて、肩コリを根本から解消することができるのです。さらに「体重を乗せてない脚」は悪い影響がでやすいため、「荷重足」「非荷重足」を見極めて筋肉のバランスを整えます。
背骨や骨盤のゆがみを整えて根本原因を解消することで、「体が動きやすい状態」をつくります。
2.鍼灸
鍼灸治療には「東洋医学的なアプローチ」と「西洋医学的なアプローチ」の2種類があります。あなたの肩コリの原因が、体のなかにあるときは「経絡の流れ」を考慮した、東洋医学的アプローチをおこないます。筋肉や関節が原因となるときは「運動連鎖」を考慮した、西洋医学的アプローチをおこないます。
鍼灸をおこなうことで「気血津液」や「血液の流れ」が良くなり、体の芯からリラックスすることができます。
3.楽トレ
特殊なトレーニングマシンを使用して、通常では鍛えにくい筋肉(インナーマッスル)を鍛えます。体幹を支える筋肉(インナーマッスル)は、ヨガやピラティスといった運動を継続しないと効果があらわれません。楽トレは「30分寝ているだけでインナーマッスル9000回分の運動効果」が獲られるため、年齢に関係なく良い姿勢を支えるための筋肉を強化することができます。
姿勢を支える筋肉(インナーマッスル)を強化することで、「楽に良い姿勢」がとれるため背骨の健康をベストな状態でキープすることができるようになります。
(柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師 藤井康徳 監修)